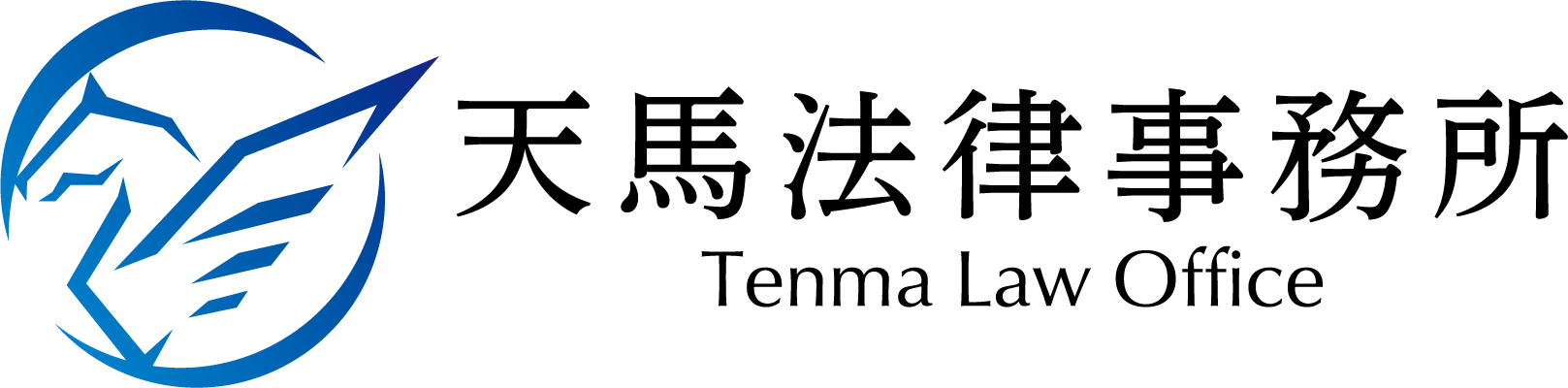近年、弁護士資格を有していながら、国の省庁や地方公共団体の職員として採用され、正規職員として働く弁護士が増えています。
このような話をすると、「どうして弁護士が公的な団体の職員になるの?」「弁護士も自営では食っていけないのか?」という疑問を持たれる方もいるかもしれません。
このコラムでは、地方公共団体(市役所)において任期付職員として5年間勤めた者として、その経験の一部と雑感等を書きたいと思います。
1 自治体は、どうして弁護士を職員として採用するのか?
内容を表示する
自治体(主に「市町村」を想定しています。)が弁護士を職員として採用する主な理由は、端的に言えば、「自治体は法律問題の宝庫だから」です。
例えば、あなたが自治体職員であるとして、上司から次のような指示を受けました。
「市内のA町にある健康増進センターを廃止し、その後、市有地であるセンターの敷地は(有償で)売却し、建物は(無償)譲与する方向で検討をしている。しかも、A町内会から、しばらくの間は健康増進のための施設として引き続き使用したいという要望も出ている。この方向で問題を整理してもらいたい。」 比較的よくありそうな事例ですね。
この事例では、「整理してもらいたい」という一言からでは想像できないような、色々な検討(法的な問題を含む。)を要します。
第一に、仕様書や契約書で色々な工夫をしなければならないというのは想像ができますね。この場合、当面の間は健康増進のための施設として使用するということになるので、売却(譲与)後の用途制限の問題が出てきます。そのため、契約書には適切な用途制限の規定(契約違反時の制裁規定等も含む。)を定める必要があります。その際には、その規定が無効とならないように検討するのは当然として(それも担当者にとって簡単な話ではありません!)、その規定によって生ずる他の影響にも配慮しなければなりません。
第二に、健康増進施設としての機能を譲渡先が担うのであれば、譲渡先候補となる企業等の意見公募等を行うことにより、より良い施設の在り方を探究する必要があるでしょう。その方法・タイミング等についても適切に検討しなければなりません。
第三に、健康増進センターを廃止することから、センターに係る条例の廃止又は改正が必要となります。それに合わせて規則の改正も必要でしょう。また、建物を無償譲与するという観点から、地方自治法第96条第1項第6号に基づく議決の要否も検討します。
他にも様々な検討を行う必要がありますが(例えば、上司の指示には含まれませんが、「売却・譲与」ではなく「貸付」による場合との比較はしておくべきでしょう。)、担当者にとって特に厄介なのは第一の点にあると思います。これは、契約書の特約条項を作ることに慣れていない自治体職員にとってはなかなかハードルの高い仕事です。こういう契約書の記載の問題等については、あまり顧問弁護士に尋ねるような内容でもありません。
こういう時に弁護士職員がいると、類似ケースの分析や関連資料の提供等を通じ、必要な情報提供を的確に行うことができますし、案件によっては弁護士が作成することもあります。一旦担当者が作成した契約書案の添削をしたり、議論をしながら契約書案をブラッシュアップしていくことにより、職員のスキルアップにもつながります。そして何より、弁護士との議論や弁護士による確認を経て事業を進めていくことができることから、職員が職務を遂行するに当たって、自信をもって職務に当たれるようになります。
このように、自治体側としては、①すぐに弁護士に相談でき、②法律問題を解決でき、③職員のスキルアップにつながり、④弁護士からの助言をもらうことで職員が自信・根拠をもって仕事を行うことができるという点で、単に目の前の事案が解決したということ以上に(目に見えない)効果があるものと判断していると考えられます。
2 弁護士が自治体職員になる理由
内容を表示する
弁護士が自治体職員(公務員)になるという話を聞いた方の中には、「弁護士が自営業では食えなくなってきているから公務員になっているのか?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、そのような金銭的な理由で自治体職員となった弁護士を、私は一人も知りません。確かに、収入面で「安定している」というのは間違いがないですが、自治体職員としての給与の額は、一般的には普通の弁護士(いわゆるまちべん)の稼ぎと比較すれば低めであると思います。
では、なぜ私が普通の弁護士から自治体の弁護士職員になったのかと疑問に思われるかと思いますが、主な理由は2つあります。
1つは、弁護士としての幅を広げるために、(若いうちに)新しい経験を積みたいと思ったことです。この弁護士職員の制度では(自営業者としてではなく)公務員として組織の中で働くことになりますから、従来型の弁護士事務所とは全く異なる業務形態となります。普通の弁護士としてだけ仕事をしていると、組織の中で人がどのように動き、議論がなされ、決定されていくのかという過程を体感することは難しいことから、そういう経験をしておきたいと考えたからです。
もう1つは、この自治体の弁護士職員という業務分野自体が比較的新しい分野であり、非常に興味深く感じられたことです。実際に、自治体内において、(重大な相談から“ちょっと確認したい”というものも含めて)本当に多様な相談を受けました。見たこともない法令の解釈を検討することもありました。現場を他の職員と一緒に訪問し、事実確認等の作業をすることもありました。これらの業務はそれ自体が普通の弁護士としては経験しがたいものでしたし、他の職員と協働して問題を解決していくことの面白さを体感することもできました。
以上はあくまで私の経験に基づく話ですが、自治体内で働く多くの弁護士は、弁護士としての経験の幅を広げるといった目的や、普通の弁護士では体感できないやりがいを求めて、自治体職員になることを希望するのではないかと思います。
3 弁護士職員のある1日の例
内容を表示する
08:30~ 勤務開始。担当課より前日の夕方に受けた苦情案件があるので急遽相談をしたいという連絡があったため、担当係長らとの法律相談を実施(40分程度)。その後すぐに、相談結果を簡単にまとめた書面を作成し、担当課に送付(15分程度)。
軽易な相談を除き、基本的に相談結果を書面でまとめ、後の決裁に活用してもらうようにしています。
09:30~ 前からの相談案件(行政処分関係)について、継続相談を実施。事実関係の確認を行い、収集すべき資料や今後の見通し、調査のポイント等を議論(1時間程度)。
重大・複雑な案件は、担当課・弁護士職員の双方が納得いくまで相談を繰り返します。こちらも市の職員なので、担当課も時間を気にせず十分に相談できます(顧問弁護士との違い)。
10:45~ 契約の検査を担当している課から、「業務委託先の個人が亡くなったから、現在の契約の効力や必要な手続きを教えて欲しい」という依頼があり、緊急の法律相談を実施(約10分程度)。その後の予定が迫っていたことから、確認・調査してもらいたい事項等を口頭でアドバイス。
緊急案件は、10分程度でもすぐにアドバイスします。顧問弁護士と違い、事前のアポイントメントがなくても、まずは話を聞くことができます。
11:00~ 訴訟案件について、関係課と共に委任先の顧問弁護士とオンラインで打合せ(約30分)。顧問弁護士との打合せ終了後、引き続き関係課と協議を行い、弁護士の指示事項や今後の作業内容・役割を確認(約30分)。
訴訟事務は外部の顧問弁護士に委託し、弁護士職員は、担当課と顧問弁護士の橋渡しの役割を担います。その際には、担当課が顧問弁護士の話をきちんと理解できているかをフォローアップするとともに、関係課から聴取した情報や入手した資料等を顧問弁護士に正確に伝達することを心がけることにより、担当課も顧問弁護士も業務をやりやすくなるように留意しています。
【昼食】
13:00~ 消費生活センターにて、相談員向けの講義(勉強会)。「詐欺」をテーマにした講義と、架空のケースを基にどのように相談者に対応・回答するかという事例検討を実施(2時間程度)。
職員教育も弁護士職員の重要な役割の1つと認識しています。
15:00~ 情報公開条例に基づく開示請求に対する対応について、担当課から相談したいという依頼があったことから、法律相談を実施(約20分)。不開示事由に関する考え方や、不開示理由の書き方等をアドバイス。
情報公開等については、正確に対応しなければ審査請求や訴訟に発展する可能性があります。微妙な案件に関しては、必要に応じてアドバイスを行います。
15:30~ 教育委員会からの相談申込みがあった件について、裁判例等の調査を実施。翌日の法律相談に向けて、基本的な考え方や今後の方向性等をまとめた資料を作成する(約1時間)。
前もって法律相談の申込みを受けた案件については、軽易な案件等を除き、事前に類似事例や裁判例、関連資料・書籍等の検討・分析を行い、検討書面を作成した上で、法律相談に臨みます。こうすることにより、こちらの考えを的確に担当課に伝えられるからです。なお、事実関係が比較的明瞭な案件については、書面での回答で解決するケースも少なくありません。
16:30~ 市営住宅における家賃滞納事例や入居者無断退去事例について、今後の方針を検討(約30分)。
懸案事項については早めに声をかけてもらい、一緒に検討を進めます。私は市当局側の議会対応事務の一部を担当していたので、議決を要する案件をあらかじめ把握しておくという効果もあります。
【勤務時間終了】
17:45~ 有志職員との法律ゼミを実施(約1時間15分)
業務と直接の関係がない法律(憲法・民法・行政法・地方自治法・刑法)を一緒に学習したいと希望する職員を募ったところ、20名弱の申込みがありました(新規採用職員~部長級職員まで)。基本的に、勤務終了後に2週間に1日のペースでゼミを実施していました。特に、若手職員の成長ぶりには驚かされました…!
★条文解釈等の軽易な問題については、立ち話の形で随時相談を受けていました。
★ここに出てきていない主な業務としては、議会関連業務(当局側)、公印業務、行政不服審査関係業務等があります。
4 自治体から求められる弁護士(自治体にとって使いやすい弁護士)を目指して
内容を表示する
私が弁護士職員として受けた相談事項の多くは、自治体の規模の大小にかかわらず発生している問題であると思われます。そして、もし弁護士職員がいない自治体の場合、「おそらくこんな感じなのではないか…?」と“根拠の乏しい判断”して職務を行っているか、問題を見なかったことにしていることが多いのではないか…?と思います。
もちろん、自治体の規模によっては、弁護士職員を1名採用することによる予算の問題があるのではないかと認識しています。ただし、弁護士が“役所の中で”“職員の身近な存在として”相談に応じることの重要性は明らかであると思いますので、街弁がそのような役割を代わりに担う仕組みづくりは不可欠であろうと感じています。
週1~2日のペースで定期的に普通の弁護士が市役所に出向くということは、関西地方の自治体を中心に広まりつつありますが、弁護士の人口が少ない地方でそのような活動を実現できないのかという点に強い関心を持っています。
極めて先進的な取組であり、非常に多くの困難があることは想像に難くありませんが、時間的・金銭的問題を調整・解決しつつ、自治体から求められる弁護士としての活動を進めてまいりたいと思っています。
この記事をお読みになり、興味があるとお感じになった自治体関係の方につきましては、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。